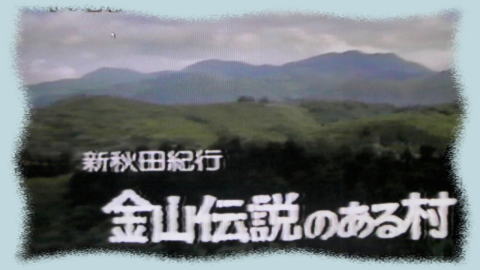昭和56年にNHKで放映された「金山伝説のある村」
気がつくとあたり一面にヒグラシが鳴きはじめて、暑い夏の一日が終わろうとしていた。
その金鉱跡は、真昼岳の麓の谷合にあって、親戚宅にはそれらしい地図も残ってはいたが、数十年来だれも訪れておらず、探索は困難を極めた。
我々は早朝に麓の村を出発したが、昔の作業道らしき道は熊笹で覆われており、車を乗り捨ててからすでに数時間がたっていた。ようやく夕暮れ近くなって、現場への目印となる、かつて鉱夫が選鉱に使っていたといわれる谷川の流れに出た。
岩魚が走り回る沢を上り切ると、突然広場が現われ、中央には夏草に埋もれて眠るように、苔むした碑が一つ立っていた。石碑は落盤事故犠牲者のための慰霊碑で、父の幼少時の記憶に比べてはるかに小さなものであったが、裏側には建立者である曾祖父の名がはっきりと刻まれていた。坑道は広場正面の斜面にV字状に二本あって、入り口こそ崩れていたが、石英粗面岩の岩盤をくり抜いて山中深く伸びていた。
父が、危ないから奥へ入るなと言ったが、どうしても中を見てみたかった。
百年の時を経た素掘りの金鉱は、人一人がやっと歩けるほどだったが、ひんやりとして当時のままに時が止まっているのを感じた。
私の本籍は、近年まで秋田県中央部の大曲市に程近い仙北郡千畑村という寒村にあったが、父ですら生まれも育ちも縁がないこの地に本籍を置いていたのには、一つのこだわりがあった。
私の先祖は、江戸初期から代々戸澤三七を名乗り、名字帯刀を許され、見渡す限りの田地田畑を所有するこの地の庄屋であった。
私の曾祖父にあたる第八代戸澤三七は、幕末の動乱期に生まれたが、アイデアと野心にあふれた男だったと聞く。
晩年になってから、真昼岳の麓にある自分の持ち山である通称「紫山」に目をつけ、金発掘事業を始めた。
もとよりこの地には金にまつわる伝説が古くからあり、源義経が落ち延びて金を掘ったというような言い伝えまであって、当時付近には何個所かの金鉱も実在していた。
曾爺さんの金山も最初は金が出たらしいが、その後はかばかしくなく、所有地を切り売りしながら二十年余鉱夫を使って掘りつづけたが、全てを失ってもついには金脈にたどり着かなかったという。
私は三七の直系であるが、曾祖父の没落後は一族離散し、今ではわずかな遠縁筋が千畑村に住んでいるのみで、前出の本籍は八代三七の墓所である。
三七金山の話は、子供のときから父に幾度となく聞かされていたが、ある夏、父を誘って曾祖父の夢の残骸を探しにいった。もうずいぶん前のことである。
その父も平成三年に他界してしまったが、最近半導体製造装置の一種であるスッパタリング装置に、高周波を印加するための高周波電源装置を開発して試験したとき、真空蒸着釜の中で立ち上る、金薄膜生成のための紫色に輝く金プラズマの光を見て、亡き父の言葉をまざまざと思い出した。
「三七爺さんの紫山の名の所以は、山に太陽が沈むとき、山に眠る金鉱脈が紫のイオンを放ち、山の稜線を紫色に染めることにある。」
あの夏の帰り道、ちょうど紫山に夕日が沈みかけていたときだった。父はそういって、金イオンが紫色であることを私に説明すると、黙り込んで山を見つめていた。
私も手をかざして山を振りかえってみたが、山並みを赤く染めた夕焼けが美しいだけだった。
いまや完全に死語となってしまった男のロマンも、明治という舞台背景には似合っていたのかもしれない。
彼は金山で巨富を築くことはできなかったが、ひたむきな信念と情熱は、現代人に失われつつあるものではなかろうか。
子孫の私には彼を責めるものは何もない。薄暗い廃坑に足を踏み入れたとき、爺さんの熱い思いが伝わってきたような気がしただけである。
しかしながら、人生もまた一生が金山掘のようである。
長い道程の中で、時には金塊を得、時には挫折する。
人は金を掘る事を諦めたとき、その人生はつまらないものになってしまうのではなかろうか・・・・